
| OK模型 ZERO SEN 30K 作製記 弐 |
|
|
|
|
| 機器搭載 2022/01/23 | |
| 主翼後部の固定箇所は桜の木を接着しネジ穴加工。 接着だけだと剥がれるような気がして不安なので側面からネジ止めしました。 昇降舵・方向舵そして普段付ける事の無いエンジン制御用サーボを組付けました。 |
|
| 燃料タンク。 およそ30年前の京商のスカイマスター10の作製以来です。 |
|
| 燃料タンクを組み立てました。タンク内の上下への配管が難しかったです。ふとした時に上下を間違えそう。 | |
| ここにどうぞ!と言った感じで穴が加工されておりましたので素直に収めました。 | |
| いよいよ直接エンジンの作業にはいります。 まずは細かい事は後で考えるとして図面通りにエンジンを取り付けてみました。 |
|
| 2サイクルか4サイクルか・・・エンジンのサイズや構造で何かと事情が変わると思うのですが素直に取り付けてみた結果・・・エンジンとホースとタンクの間が狭すぎるような・・・。 | |
| スロットルの位置がなかなかタイトな場所にあります。 | |
| 胴枠にリンケージ用の穴をあけエンジンにリンケージを繋げてみました。 どうしても必要と言うわけではないのですがエンコンリンケージ確認用の窓を空けました。 |
|
| リンケージの取り回しの関係でエンコン用のサーボを上下逆につけなおしました。 | |
| エンジンの種類や取り付け方法によって色々と考えなければいけないようです。 | |
| エンジンマウント用の桜木材の上に受信機バッテリー固定用のマジックテープを取り付けました。 | |
| 受信機用バッテリーを取り付けてみました。 | |
| 機首内部 防火壁裏側の空きスペースに受信機とレギュレーターを両面テープ留めしました。 | |
|
|
|
|
樹脂パーツ加工 2022/01/24 |
|
| 樹脂パーツの加工を行っていきます。 操縦席前面のパーツです。 |
|
| 風防は前後一体成形のシンプルなものです。 窓枠の形状はまぁまぁ合っているようです。 |
|
 |
機首上面パーツと風防を接着し一体化しました。 機体にネオジムマグネットを埋め込み風防に使用済みカッター刃を貼り付けました。 窓枠は後の塗装が透けるのを防ぐため窓枠内部を機内色で塗装してあります。 |
| 風防を機体に取り付けてみました。 搭乗員は以前ヤフオクで購入したものです。サイズ的にやや大きめですがさして違和感はなさそうです。 |
|
| エンジンカウルは樹脂パーツ組み合わせです。 経年劣化か日焼けしている箇所が脆くなっております。 切り出しの途中で意図せぬ箇所に亀裂が入りとヒヤヒヤ。 |
|
| 切り出してからパーツを接着、とりあえず何とか形にはなりましたが・・・ガラス細工並みに取り扱い注意です | |
| 2サイクルエンジンであればカウルの中に収ったかも知れませんが今回は音質重視の4サイクルなのでカウルをカットしヘッドが見えております。 現物合わせでカットしていく間も思わぬ亀裂が入りどんどん大きくなってしまった。 |
|
| 機首部にテープで固定してみました。 全景が見えて参りました。 |
|
|
|
|
| 二一型へ変更 2022/01/24~02/06 | |
| パキっ!!!! カウル固定用のネジ穴を開けている時に大きく空きました。 |
|
| パリっ!!!! 逆側面も割れました。 まぁ、この状態で実際にFLTに耐えられるか不安でしたのでかえって踏ん切りがついたような・・・。 |
|
| とりあえず我が家の在庫で作るか使えそうな物を・・・。 何かの折に使えるかと長年温めていたFMS BiG零戦二一型のカウル。 あいにく零戦二二型用のカウルは無く、ラジコン1でも在庫切れで入手時期不明なのでこちらが使えるといいんだけど・・・。 |
|
| 二一型のエンジンカウルに変更した事でエンジンの位置合わせが必要となり10mm前方へ移動しました。 元々燃料ホースのクリアランスが狭かったのでいずれ位置合わせが必要と思っていたので丁度いい。 |
|
| 反対から見ても燃料ホースに無理のない様子。 | |
| カウルが割れた時はどうしよう!となりましたが無事におさまって良かった。ついでに二二型よりは思い入れのある二一型にもなったので怪我の功名です。 | |
| 二二型と二一型では七.七粍機銃口の開口部が違うので機首上面を合うように加工していきました。 | |
| 基本的なシルエットは同じなので大改修にならずに済みました。 | |
|
|
|
| 塗装 2022/02/06~10 | |
| 通常は生地にフィルムをアイロンで貼り付けるのだと思うのですが私はフィルム貼りの道具やノウハウを持っておりません。 なのでアルミテープ貼りです。 さて、生地状態にアルミテープを貼ったらいくら重量増となるか? 胴体はエンジンやサーボ等込みで1,326gから0.02mmテープ貼り付けで1,351gと25g増量、主翼はサーボ込みで800gから0.03mmテープ貼り付けで838gと38g増量となりました。 仮に0.05mmアルミテープで行えば約4倍の増加量になります。 |
|
| 二一型の色調や機体全体のディティール等を考慮し今回はあっさり目にモールドを入れております。 この時点ではリベット表現はディティール全体として不釣り合いと感じたのでパスしました。 |
|
| アルミテープに塗料の食いつきをよくするためあらかじめミッチャクロンを吹きかけ機体色であるタミヤAS-29スプレー 灰緑色吹き付けました。 二一型となった事で塗装も塗り分けの必要がなくなり楽になりました。 |
|
| 警戒ラインの赤、カウルの青黒、尾翼の黄帯を塗装しました。 | |
| 日本海軍 第1航空戦隊 空母赤城搭載 AI-102 部隊塗装はどこの誰にしようか色々と悩みました。 ベタな選択ですが真珠湾攻撃時の進藤三郎大尉機としました。 |
|
| 日の丸ステッカー貼り付け。 元は二二型用なので主翼の日の丸が少し大きいような・・・。 |
|
| エンジン機は燃料により塗装が痛むようなのでガードするために耐油性のウレタン艶消しクリヤーを吹きかけました。今まで二液混合のスプレーは使用した事がなく、またタミヤスプレーの上から吹きかけても大丈夫かどうかの検証をすっ飛ばしてしまった。 とりあえずぶっつけ本番でやってみました。 ひとまずタミヤカラーへの上塗りは大丈夫なようです。 耐油性はこれから検証です。 |
|
|
|
|
| 工場出荷 2022/02/10 | |
| 重心がやや後方のためバラストを150g分載せました。 | |
| ホント二一型のカウルを在庫していてよかった。 偉いぞ過去の私・・・。 ペラはキットの推奨が4サイクルの場合は10×6の2ブレードだったのでまずは素直にこの仕様で色々と慣れていこうと思います。 |
|
| いつもの電動機とは違う雰囲気。 眺めているだけで妙にそわそわします。 |
|
| 零式艦上戦闘機二一型 4593號 工場出荷 全長:990mm 全幅:1,320mm 機体重量:2,591g 翼面積:27.0dm2 翼面荷重:95.96g/d㎡ 真珠湾攻撃時はまだ二一型の故障ではなく零式一号艦上戦闘機二型と呼ばれていました。 |
|
| 通常であればめでたく完成!ではFLTへ!っと思うところなんですが・・・ 原動力であるエンジンの本質にまだ全く触れていない。 試せていない・・・・昭和であれば玄関先でエンジンをぶん回して地上での慣らしを済ませてしまってから現地へ!って事ができたかもしれませんが令和の今にそんな事をしようものなら各方面からお叱りを受けてしまいます。 なので時期を見て飛行場で本を片手にボチボチと準備していきたいと思います。 |
|
|
|
|
| 3枚プロペラ 2022/02/11 | |
| 2ブレードだからなのか機首に何かしらの違和感を感じます。 せめて飾っている時だけでも何とか見栄を良くしたい。 キットをいただきエンジン機に挑戦してみようと思った時にはそういうものだと感じていたのですが完成が近づくに連れて見方が変わってしまいました。 飛びの2ブレードと割り切れば・・・実際そういう世界なのだろうけどなかなかそう大人の物わかりの良さを体得できていません。 FLTを重ねる事ができればこれはこれで色々な考えがリンクし納得できる志向に落ち着けるのかも知れませんが・・・暇々なので余計な事ばかり考えてしまう。 |
|
| MAの12×6 3ブレードペラ エンジン用を購入してみました。 もしかしたら後に3ブレードでFLTする一縷の望みを託せるかも!と下心満載。 今あれこれ思うよりせめてエンジン回して回転数等のデータ取りしてダメなら仕方ない。 やるだけやった後ならあきらめもつくだろう。 |
|
| 機体の推奨だとペラは10×6となっていましたがエンジンでの推奨はスケール機の場合は12×6~8、13×6~7となってます。 この場合、どちらに合わせればいいのやら・・・まぁ、これらは試す機会があれば次々やってみよう。 ちなみに2ブレードのスピンナーでは12×6 2ブレードは取り付ける事ができませんでした。 スピンナー的に推奨外って事か? とりあえず先端の角を削って丸くしました。 根元が太めですが後々の希望も託しているのでこれで十分。 回転バランスを取りシルバーに塗装し先端に赤の2本ラインを入れて飾り用ペラのできあがり! |
|
| やはり3ブレードの方が自然だな~。 ただ今度はスピナーの形状が気になったりして・・・本質でないものに捕らわれ過ぎかな! |
|
| これで飛んでくらたらと思えども・・・未だにエンジンの始動さえもしていないのに夢見過ぎ。 暇を持て余すと碌な事を考えません。 |
|
|
|
|
| 日の丸適正化 2022/04/16 | |
 |
とある日、クラブの飛行場にて・・・「主翼の日の丸・・・少し大きくない!」 とご指摘を受けてました。・・・やはり気付かれた・・・。 確かに大きいんですよ!自分の中でも違和感アリアリで・・・でも直そうかどうしようか考え中でした。 この機体を作っている当時は細かい考証まで頭が回らず付属のステッカーをそのまま貼っていました。 ほぼ同じ主翼の二一型と二二型ですが日の丸のサイズは違うんですね! |
 |
主翼の日の丸、実機のサイズは880mm この機体は1/9スケールなので約98mm。 今貼ってあるのが120mmなので2回りほど大きいですね。 |
 |
ちなみに胴体側面の実機でのサイズは750mmです。 すでに貼ってあるものでサイズ感はあっています。 |
 |
貼ってあった日の丸を剥がしました。 |
 |
ステッカーと同時に塗料も剥がれました。 使い切ったスプレー缶を集めて最後の一息を絞り出し剥げた箇所を塗装。 |
 |
カッティングシートで新たに直径98mm日の丸を切り出しました。 |
 |
貼り付けて作業終了。 あぁ!これでしっくりきました。 この比率ですわ! |
|
|
|
| 発動機始動・慣らし運転 2022/05/08~06/04 | |
| 初始動 2022/05/08 | |
| いよいよエンジン初始動です。 | |
| 1993年のスカイマスター10は経験としてはノーカウントって事にして実質初めてエンジン機に挑む心境です。 | |
| 燃料入れて・・・プラグヒーター付けて・・・スターターを押しつけてブルン!!!で無事に回りました | |
| 感慨深いと思いながらスロットルに少し触れたら止まってしまった。 ここから次が全然かかりません。 見かねたクラブの先輩からからアドバイスをもらい助けていただきました。 原因は単3乾電池が電源のプラグヒーターの電池切れ・・・ |
|
| 現場にいらした方から立派なプラグヒーターをお借りし始動したところ再度アッサリとかかりました。 電池式プラグヒーターは電池1本で一日は持つかと思っておりましたがおそらく4、5回トライすると電池はお終いのようです。 エンジン慣らし中・・・インターバルに両名から色々と教えていただく。 過回転・・・このエンジンに対してペラが小さすぎとの事・・・やはり機体の推奨よりエンジンの推奨が優先か・・・。 あまり合わないペラでニードル調整やペラ回転数チェックしてもデータとしてはアレなんでとりあえず今日のところは慣らしのみで終了です。 |
|
| 燃料の排気で貼ってあったアルミテープが剥がれてしまった。要対策です。 熱いエキマニの直近にあるニードルをどうやって調整するのだろうか? 次までに調べておこう。 |
|
| 13×6 2ブレードペラ 慣らし中にエンジン機のベテラン様が様子見に来てくれました。 やはりペラサイズやエンジン推奨に機体推奨、年代によるエンジンサイズがその当時の推奨と現代の推奨と違う等など・・・色々とあるようです。ベテラン様からエンジン推奨値のペラを一ついただきました。ありがとうございます。 |
|
| ペラ変更 2022/05/13 | |
| 装着していた10インチペラと頂き物の13インチペラ。 OS DS-α56Ⅱの推奨値は12~13インチ・・・機体推奨の10インチという値に捕らわれすぎました。 元々空モノRCは様々なマテリアルを組み合わせて完成を目指していたが多いはず・・・ですが最近はメーカーの出来合いモノにすっかり慣れてしまい自分で考える事が疎かになってしまいました。 推奨値を外れたペラで調整しても無意味なので今回はしっかり13インチで合わせていきます。 |
|
| スピナーはペラと合わせてOK MODELストアに推奨であったものですがペラが12インチ以上となると取り付ける事ができません。 | |
| なので新たにスピナーを購入しました。 | |
| さっそく機体に装着。なんだろ・・・この感覚。 今まで2ブレードだと不格好と思っていました。 2ブレードだったからカッコ悪く見えていたわけではなく・・・ こうして見ると以前までペラもでしたがスピナーもスケール的に小さかったのだなぁと思います。 ペラとスピナーが適正になった事でラジコン零戦としてはこのまま2ブレードでもかまわないんじゃないかと思えてきました。 スピナー的には3ブレード用に揃えたものより断然カッコイイ。 |
|
| ABC HOBBY プラグヒーター スピナーと共に新調。 単3電池式はアッサリとエネルギー切れを起こすため改めて購入。 |
|
| ニッカドでそれなりに容量もあるのでこれで充分かと! 充電時間が8時間なのは昔とあまり変わらないなぁ。 プラグヒート通電中に電流値が見えるので点火しているかどうかわかるので私のような素人にはありがたい。 |
|
| 発動機2回目試運転 2022/05/15 | |
| 2回目のエンジン試運転です。 ペラを10×6から13×6に変更しデータ取り。 相変わらずモタモタしながらも始動は簡単に行えるようになりました。 まずはカウルを外した状態で回転数を確認。最高8,000~9,000程・・・ベテランの話だと妥当だそうで安心。 スローでプスンと止まるのでスロットル範囲調整・・・とりあえず上手くいくようになりました。 |
|
| 次にカウルを装着しエンジンスタートしたところ中速まではOKなれどフルに近づくと怪しくなり止まってしまう。 2度試して同じようなタイミングでストップでした。 クラブの先輩方の意見としてはオーバーヒートではなさそう。空気取り入れ口も問題ない。 ニードル調整 要かな!っとのこと。 まだカウル装着時にニードル調整ができない状態なので次までに加工してきます。 |
|
| ニードル調整ノブ追加 2022/05/17 | |
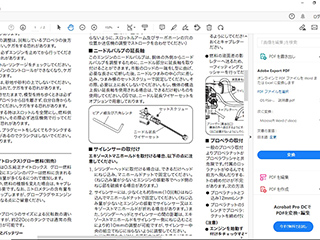 |
エンジン回転時のあの厚い状態でニードル調整はどのようにやるのだろう?っと思っておりましたが説明書にきちんと書いてありました。 |
| その前にクラブの先輩から「余ったレンチを差し込んで固定するんだよ」と教えてもらっていました。 はて?そんな都合よい作りになっていたかしら・・・ |
|
| ありました。 言われるまで全く気付きませんでした。 |
|
| 曲げ加工を施した1.6mmピアノ線を差し込んで固定。 | |
| カウルに穴あけ加工をして装着しました。 これでカウル装着時にもニードル調整できるし熱いのも避けられます。 めでたし♪めでたし♬ |
|
| 発動機3回目試運転 2022/05/29 | |
| なかなかエンジンがかからず四苦八苦。 色々と助言をいただきどうも燃料流量が多すぎたようです。 前回までより気温が上がった影響があるようです。 エンジンは生き物!?その時々で色んな現象があるようで慣れるしかありません。 エンジン自体はだいぶ仕上がりましたが強風で初FLTは断念しました。 |
|
| 燃料タンク内ホース変更 2022/06/04 | |
| おもりの付いた燃料ホースが追従性が悪いと背面状態で吸う事ができなくなる! なるほど・・・ごもっとも! 使用していたホースを見た先輩からその可能性があるとご指摘が! ちょうど合うホースを分けてくれました。ありがとうございます。 ロールやループと背面状態になるFLTがいつできるようになるかはわかりませんが頑張ります。 このIMのホースがマストアイテム・・・とどなたかの声が聞こえたので今後これ以外は買わなくなると思います。 |
|
| さっそく分解。 | |
| ホースを交換しました。 | |
| 燃料タンクを外すためエンジンを下したのでこの際、木材むき出しだった部分をタミヤのポリカ用スプレーで塗装しました。 | |
| 日に照らされ続けると貼ってあるアルミテープが伸びてフカフカ・・・。 おそらく生地に含まれている空気が膨張し浮かせてくるのもあると思います。 もう少し厚いテープだとこうはならないのですが重量との兼ね合いで致し方のないところです。 |
|
| とりあえず手で撫でまわして皺ができないように整えます。 どれだけ効果があるのかわかりませんが空気抜け用としてルレットでコロコロしてリベット風に穴をあけました。 |
|
| 受信機スイッチは見てくれを重視し内装にしていましたが作業を始めたり終わったりの度に風防を外すのが手間なのでスイッチを外装に取り付けました。 | |
|
|
|